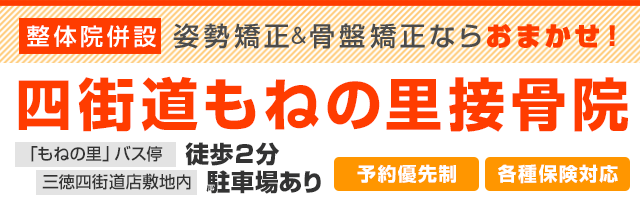巻き肩

こんなお悩みはありませんか?

首と肩の筋肉が張って動きづらくなったり、気になってしまう
デスクワークが多く、時間が経つにつれて前のめりになっている
猫背が酷いと言われる
肩が首よりも前に出ている
肩甲骨が出てこない
頭痛が起こる
などのお悩みはございませんか。
このような方は巻き肩になっている可能性が考えられます。
日々の姿勢を意識することもそうですが、少しでもお悩みの方は接骨院などの専門家に一度ご相談されることをおすすめします。
巻き肩について知っておくべきこと

巻き肩は、肩が前に出過ぎた状態です。姿勢の悪さや筋力の低下、就寝時の姿勢などが原因で起こります。慢性化しやすいため、気づいた時点で早めに対策を始めることが大切です。
・首や肩のこり、頭痛、ストレートネックなどが起こる可能性がある
・呼吸が浅くなり、疲労感・眼精疲労・代謝の低下を引き起こす原因となる
・猫背につながったり、肩こりや首こりが発症する可能性がある
・肺が広がりにくく、酸素が十分に取り込めなくなり、学力の低下や運動パフォーマンスの低下、疲労回復力の低下にもつながることがある
【巻き肩のセルフチェック方法】
・横から見て腕が耳より後ろにあれば正常。前になっていれば巻き肩の可能性がある
・まっすぐ立って腕を自然に垂らした状態で、肘の位置が外側に向いていれば巻き肩の可能性が高い
症状の現れ方は?

巻き肩になると、肩や首の痛み、頭痛、めまい、耳鳴りなどの症状が現れることがあります。また、呼吸が浅くなったり、内臓の不調や腰痛などの原因にもなることがあります。
【症状】
・肩や首の痛み、肩こり
・呼吸が浅い
・疲れやすさ
・内臓の不調
・腰痛や下肢の痛み
・頭痛、めまい、耳鳴りなどの自律神経症状
【原因】
・肩甲骨が前方に突き出し、肩が内側に巻き込まれる姿勢になる
・肩甲骨の筋肉や関節のバランスの崩れ
・長時間のデスクワークやスマートフォンの使用などによる前かがみの姿勢
・上半身の筋肉のバランスの崩れ
【影響】
・肩関節が硬くなり、可動域が狭くなる
・肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)になる可能性がある
・頚椎ヘルニアになる可能性がある
・呼吸が浅くなることで、脳や筋肉への酸素不足を引き起こす
・睡眠の質に影響を与え、自律神経系や体力面、生活活動に支障をきたす可能性がある
その他の原因は?

【巻き肩のその他の原因】
・長時間のデスクワークやスマートフォン操作による前傾姿勢
・横向きでの睡眠
・首や肩まわりの柔軟性不足
・インピンジメント(挟み込み)状態の悪化
・肩が首よりも前に出る猫背のような姿勢
・胸椎の後弯(後ろ側に骨が反る状態)の増強
巻き肩は、姿勢不良だけでなく、成長期の子どもにおいても注意が必要です。骨の成長段階では骨端が柔らかく、姿勢の影響を受けやすいことが知られています。
巻き肩を放置するとどうなる?

巻き肩を放置すると、肩こりや頭痛、猫背、四十肩・五十肩、頚椎ヘルニアなどの不調を引き起こす可能性があります。
【健康上の問題】
・肩こりや頭痛、背部痛などの不調の原因となる
・肩関節が硬くなり、可動域が狭くなる
・筋肉の硬直が進むことで、肩関節周囲炎になる可能性がある
・頚椎や軟骨が圧迫され、頚椎ヘルニアになる可能性がある
・筋肉のバランスが崩れ、身体機能に支障が出ることがある
・姿勢の悪化が内臓に影響し、消化不良や胃の不快感を引き起こすことがある
・胸郭の圧迫が心血管系への負担を増やし、長期的には心臓病や高血圧のリスクを高める可能性がある
当院の施術方法について

当院では以下のような施術を行っております。
【保険施術】
手技療法(指圧)
温熱療法(遠赤外線)
【自費施術】
骨格矯正
肩甲骨はがし
猫背矯正
自費施術にはフリーパスや回数券など、通いやすいプランもご用意しております。お気軽にご相談ください。
軽減していく上でのポイント

巻き肩を軽減していくためのポイントは、以下の4つです。
1、姿勢の意識
・耳・肩・骨盤が一直線になるように立つ
・胸を軽く開くイメージで肩を引く
・スマートフォンやパソコンの画面を目線の高さにする
2、ストレッチ
・壁を使った胸ストレッチ(壁に手をついて体をひねる)
・タオルを使った肩回し(タオルを持って前後に動かす)
・背中のストレッチ
3、筋力トレーニング
・僧帽筋・菱形筋・広背筋を鍛える
・両手を広げて肩甲骨を寄せる動作を行う
4、生活習慣の見直し
・椅子の背もたれによりかからない
・長時間同じ姿勢を続けないようにする
監修

四街道もねの里接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:静岡県浜松市
趣味・特技:おでかけ